北海道の自然が育むエゾフクロウとシマフクロウの違いと生態の秘密

エゾフクロウとシマフクロウの違いが知りたい方へ。
北海道で見られる二種は見た目や鳴き声、大きさ、食べ物まで多くの点でちがいます。
この記事ではエゾフクロウとは何か、シマフクロウとは何かをていねいに整理し、絶滅危惧に関する現状もわかりやすく解説します。
・二種の基本プロフィールと外見のちがい
・鳴き声や大きさなど識別ポイント
・食べ物と生息環境のちがいと理由
・絶滅危惧の背景と守るためにできること
エゾフクロウとシマフクロウの違いをわかりやすく解説
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ北海道に生息するフクロウの特徴
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ北海道は日本の中でも特に自然が豊かで、広大な森林や湿原が広がる地域です。
そのため、ここでは数種類のフクロウが生息しており、それぞれが環境に合わせた暮らしをしています。
代表的なのが「エゾフクロウ」と「シマフクロウ」です。
どちらも北海道を象徴する鳥として知られていますが、生態や姿かたち、そしてくらす場所にははっきりとした違いがあります。
エゾフクロウは、主に北海道の広葉樹林や針広混交林に分布しています。
顔がハート形で、頭に耳のような羽角(うかく)がないのが特徴です。
昼間は木の洞(うろ)や枝に静かにとまり、夜になると活動を始めます。
人里近くの森や公園でも見られることがあり、比較的身近な存在です。
一方、シマフクロウは川や湖のそばを中心に生活する世界最大級のフクロウです。
大きな羽角をもち、全長70センチ前後、翼を広げると1.8メートルにも達します。
魚を主な食べ物とするため、水辺の環境と深く結びついています。
特に、冬でも凍らない川や、魚が上流にのぼることができる自然の流れがある場所が、生息に欠かせません。
このように、エゾフクロウとシマフクロウはどちらも北海道の自然を代表する存在ですが、くらす環境・体のつくり・鳴き声などにくっきりとした違いがあります。
森の中で静かにくらすエゾフクロウと、水辺で力強く生きるシマフクロウ。
それぞれの姿は、北海道の自然の多様さを教えてくれます。
エゾフクロウとはどんな鳥か
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージエゾフクロウ(学名:Strix uralensis japonica)は、フクロウの亜種で、日本では北海道を中心に生息しています。
全長は約50センチ、翼を広げるとおよそ1メートル。
体全体が白っぽい灰褐色で、細い縦じま模様が入っています。
顔は淡い茶色を帯びた丸いハート形で、黒い大きな目が印象的です。
耳のような羽角がないため、柔らかく優しい表情に見えるのが特徴です。
生息と行動
エゾフクロウは夜行性で、昼間は木の洞や枝でじっと休んでいます。
夕方になると活動を始め、ネズミやモグラなどの小型哺乳類を鋭い聴力でとらえて捕食します。
夜の森でじっと動きを止めて音を聞き、地面の下を動く小動物の足音さえ聞き分けることができます。
獲物を見つけると、羽音をほとんど立てずに滑空して捕らえます。
食べ物と繁殖
主な食べ物はネズミ類ですが、小鳥、エゾリス、エゾモモンガ、カエル、昆虫なども捕まえます。
食性は非常に柔軟で、季節や地域によって変化します。
繁殖期は春(3月〜5月ごろ)で、木の洞を巣にして2〜4個ほどの卵を産みます。
抱卵はメスが担当し、オスが餌を運びます。
巣立ったヒナは1か月ほどで飛べるようになりますが、しばらくは親の近くで暮らします。
人との距離
北海道では、緑地や公園などの都市近郊にも姿を見せることがあります。
札幌の円山公園や旭山記念公園などでも確認されており、市民にも親しまれる存在です。
ただし、野生動物のため、安易に近づいたり保護したりするのは禁じられています。
野鳥は「鳥獣保護管理法」により、特別な許可なく捕獲・飼育することはできません
(出典:環境省 鳥獣保護管理法)。
静かに見守ることが、エゾフクロウの生活を守る第一歩です。
シマフクロウとはどんな鳥か
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージシマフクロウ(学名:Ketupa blakistoni)は、世界最大級のフクロウとして知られています。
体長は約70センチ、体重はメスで3〜4キログラムにもなり、翼を広げると180センチを超えることもあります。
羽色は灰褐色で黒い縦じまがあり、胸元は白っぽく見えます。
顔は幅が広く、鋭い目つきと長い羽角が特徴的です。
生息地と分布
日本では北海道の東部、特に根室地方、釧路地方、知床半島周辺などに生息しています。
国外ではロシアの沿海地方、サハリン、千島列島の一部にも分布します。
北海道内で確認されている個体数は、環境省の推定によると約200羽前後、つがい数では100組に満たないとされています
(出典:北海道森林管理局「シマフクロウ保護増殖事業計画)。
つまり、シマフクロウは日本の中でも非常に貴重な鳥であり、現在も絶滅の危機にあります。
生態と特徴
シマフクロウは主に魚を食べるフクロウで、アメマス、ヤマメ、サケなどの川魚を捕まえます。
浅瀬で獲物を見つけ、鋭いかぎづめで素早く捕らえます。
魚を食べるため、冬でも凍らない川や湧水地などが生活の中心になります。
また、営巣には数百年級の大木が必要です。
広葉樹の樹洞や、環境団体が設置した大型人工巣箱を利用して繁殖します。
巣箱は縦横1メートルを超えるものもあり、専門家が山奥に運び上げて設置しています。
絶滅危惧種としての保護
シマフクロウは「環境省レッドリスト」で最も絶滅の危険が高い「絶滅危惧IA類」に指定され、国の天然記念物にもなっています。
生息環境の悪化、河川の改修、営巣木の減少が主な要因です。
そのため、釧路湿原や羅臼などでは、給餌池(魚を補給する池)や人工巣箱の設置が行われています。
こうした活動は、環境省、北海道、そして民間の保護団体が連携して進めています。
少しずつですが、繁殖に成功するつがいも増えており、地道な努力が実を結びつつあります。
鳴き声から見るエゾフクロウとシマフクロウの違い
フクロウを見分けるとき、姿形だけでなく「鳴き声」も重要な手がかりになります。
特に夜間の観察では、音が唯一の識別手段になることもあるため、鳴き声の特徴を知ることは大切です。
エゾフクロウの鳴き声の特徴
エゾフクロウの鳴き声は、落ち着いた低音で「ホーホー」と聞こえます。日本では昔からこの声を「ゴロスケホーホー」と表現してきました。
オスは「ホーホー」とゆっくり鳴き、メスはやや高い声で応答します。
この鳴き声には、縄張りを主張したり、つがい同士が互いの位置を確認したりする意味があります。
特に繁殖期(2月〜4月)になると、夜明け前や夕暮れに盛んに鳴き交わす姿が観察されます。
声量は控えめですが、静かな森の中ではよく響き、優しく穏やかな印象を与えます。
シマフクロウの鳴き声の特徴
一方、シマフクロウの鳴き声は非常に力強く、遠くまで響き渡ります。
オスが「ボッボッ」、メスが「ボー」と鳴き、つがいで「ボッボッボー」と交互に鳴き交わします。
この鳴き声は1キロ以上先でも届くと言われ、夜の川辺に深く響く独特の重低音です。
発声には胸の筋肉と気嚢を使って共鳴させるため、まるで太鼓のような重みのある音になります。
これは縄張り宣言の意味が強く、周囲のつがいへの警告や、繁殖期のペアの絆を確認する役割を持っています。
また、幼鳥が親を呼ぶときには「ピィー」と細い声を出すこともあります。
出典:シマフクロウの鳴き声 日本野鳥の会
聴き分けのポイント
エゾフクロウの声は柔らかく、森の中でゆっくり響くのに対し、シマフクロウの声は低く太く、遠くの山に反響するほどの迫力があります。
そのため、森の奥で「ホーホー」と聞こえたらエゾフクロウ、水辺で「ボッボッボー」と重く響いたらシマフクロウの可能性が高いといえます。
鳴き声を通じて、それぞれの生息環境の違いも感じ取ることができます。
大きさと見た目で比較するエゾフクロウとシマフクロウ
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ外見の違いも、両者を識別するうえで非常に分かりやすいポイントです。
特に「体の大きさ」「顔の形」「羽角の有無」「色合い」などは、観察初心者でも見分けやすい部分です。
以下に詳しく整理してみましょう。
| 比較項目 | エゾフクロウ | シマフクロウ |
|---|---|---|
| 体長 | 約50cm | 約70cm |
| 翼開長 | 約100cm | 約180cm |
| 体重 | 約700〜1000g | 約3〜4kg |
| 羽角 | なし | あり |
| 顔つき | 丸く白っぽいハート形 | 幅広く精悍で縞模様が強い |
| 目の色 | 黒 | 黄橙色がち |
| 足の羽毛 | つま先まで覆う | 水辺向きで羽毛が薄め |
| 主な生息地 | 北海道各地の森林 | 北海道東部の河川沿い |
| 繁殖期 | 3〜5月 | 2〜4月 |
| 鳴き声 | ホーホー(穏やか) | ボッボッボー(重厚) |
大きさと体の特徴
エゾフクロウは全長約50センチで、体全体が柔らかい羽毛に包まれています。
羽角がないため、顔の輪郭が滑らかに見えます。
羽毛の模様は淡い茶褐色の縦じまで、保護色として森の木肌に溶け込むようになっています。
一方、シマフクロウは圧倒的な大きさを誇ります。
翼を広げると約1.8メートルにもなり、飛び立つとまるで鷲のような迫力です。
羽角が立っているため頭部の輪郭が鋭く、顔の中心から放射状に広がる羽毛が精悍な印象を与えます。
生息環境と体の適応
エゾフクロウの羽毛は密度が高く、保温性にすぐれています。
冬の北海道の厳しい寒さでも活動できるように、つま先まで羽毛で覆われています。
これに対して、シマフクロウは水辺で魚を捕るため、足先の羽毛が少なく、濡れても冷えにくい構造になっています。
爪は太く長く、水中で魚をつかむのに適しています。
このような身体的特徴の違いは、食性と生息地の違いをそのまま反映しているといえます。
観察時の見分け方
森の中で木の洞にひっそりととまっている白っぽいフクロウを見つけたら、それはエゾフクロウの可能性が高いです。
反対に、川沿いの岩やとまり木に大きなフクロウがいて、時折水面をのぞき込んでいたら、それはシマフクロウの行動です。
観察の際は望遠レンズや双眼鏡を使い、一定の距離を保つようにしましょう。
繁殖期や夜間に近づきすぎることは、ストレスを与える原因になります。
写真を撮る場合も、フラッシュ撮影は厳禁です。
自然のリズムを乱さないことが、共生への第一歩です。
エゾフクロウとシマフクロウの違いから見える生態と環境
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ食べ物と生息環境のちがい
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージエゾフクロウとシマフクロウは、どちらも夜行性の猛禽類ですが、食べ物の種類や狩りの方法、そして生息する環境は大きく異なります。
この違いを理解することで、それぞれの生態がどのように自然と結びついているかが見えてきます。
エゾフクロウの食生活と狩りの特徴
エゾフクロウの主食は野ネズミ(エゾヤチネズミなど)です。
耳が非常に発達しており、雪の下や草の中を走るネズミの動きを音だけで察知します。
一度獲物を見つけると、羽音をほとんど立てずに滑空し、鋭い爪で素早く捕らえます。
他にも小鳥やモモンガ、リス、カエル、昆虫なども捕食します。これは「機会捕食」と呼ばれるスタイルで、季節や環境によって食べ物を柔軟に変える能力を持っています。
こうした適応力の高さが、北海道の広い範囲で一年中暮らすことを可能にしています。
エゾフクロウがくらす森は、広葉樹と針葉樹が混じった「針広混交林」が中心です。
特に大木があり、木の洞(うろ)が形成されている場所が重要です。
繁殖期にはこの洞を巣として利用しますが、伐採や老木の減少によって巣となる木が失われつつあります。
このため、保護団体が人工巣箱を設置するケースも増えています。
シマフクロウの食生活と水辺との関係
一方、シマフクロウは魚を主食とする「魚食性フクロウ」です。
アメマス、ヤマメ、ウグイ、サケの幼魚などを捕まえて食べます。
川の浅瀬や滝つぼの下にとまり、魚が近づくと一瞬のすきに両足でつかみ取ります。
水辺に生きるため、足の羽毛は少なく、水がしみ込みにくい構造になっています。
また、爪は太く長く、水中で暴れる魚を逃さない強い握力を持っています。
冬になると、川の多くは氷に覆われます。
シマフクロウは凍らない湧水や流れのある川を選び、生き延びます。
しかし、近年は河川工事や砂防ダムの増加により、魚が遡上しにくくなり、食料確保が難しくなっています。
そのため、釧路や羅臼などでは「給餌池」と呼ばれる人工の餌場が設けられ、魚を補給して個体群の維持が図られています。
生息環境の違いのまとめ
エゾフクロウは森と木の洞があれば生きられる陸のフクロウ、シマフクロウは川と魚が欠かせない水辺のフクロウです。
同じ北海道に生息していても、必要とする環境が全く異なるため、両者が同じ場所で見られることはほとんどありません。
つまり、エゾフクロウが「森の静けさの象徴」だとすれば、シマフクロウは「川の守り神」といえるでしょう。
(参考:環境省自然環境局「シマフクロウ保全のための取組」)
北海道におけるシマフクロウの絶滅危惧状況
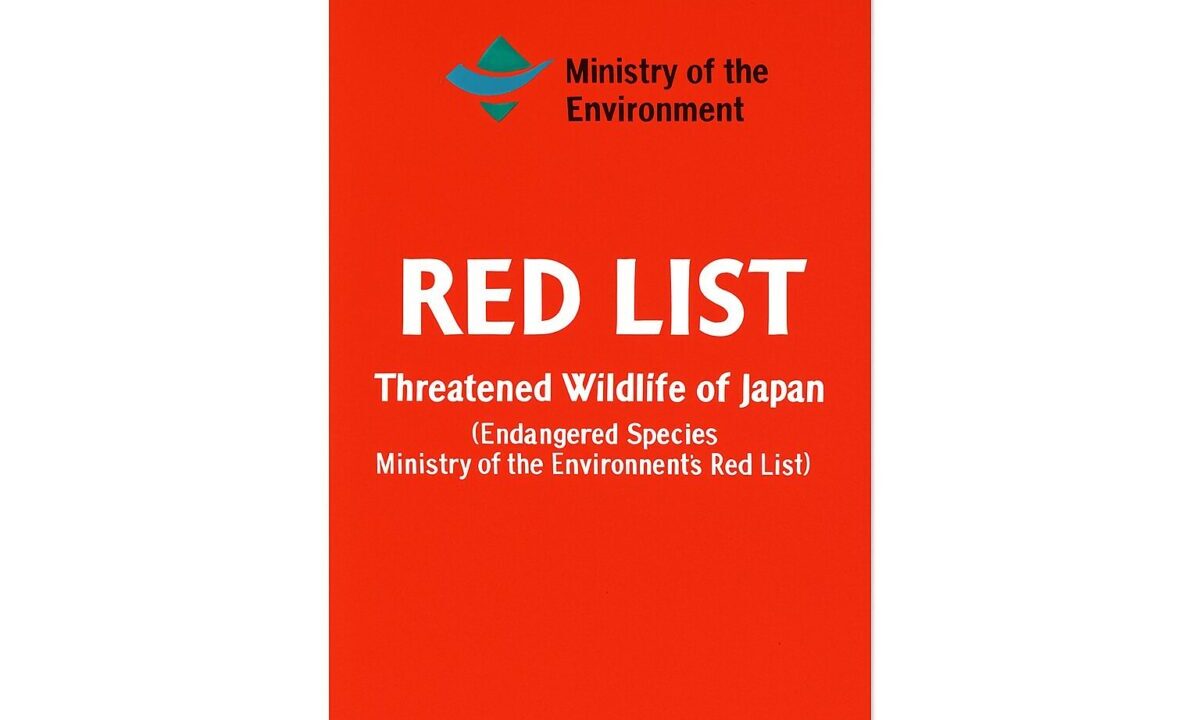 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージシマフクロウは、現在の日本において最も絶滅の危険が高い鳥類の一つです。
環境省の「レッドリスト2023」では、絶滅危惧IA類(Critically Endangered)に分類されており、国の天然記念物にも指定されています。
その個体数は、推定でわずか200羽前後。北海道の東部を中心に限られた地域でしか確認されていません。
絶滅の危機にある理由
シマフクロウが減少している主な理由は、次の三つです。
-
魚の減少と河川環境の変化
河川の直線化やダム建設、砂防工事によって、魚が上流までのぼれなくなり、エサ場が失われました。
水温の上昇や河畔林の伐採も、魚の生息に悪影響を与えています。 -
巣となる大木の減少
シマフクロウは、直径1メートルを超えるような巨木の樹洞で繁殖します。しかし、林業や開発によって古木が減少し、巣を作れる木が少なくなっています。
そのため、現在は大型の人工巣箱を使って繁殖を支援する取り組みが行われています。 -
人間活動による事故やストレス
近年では、道路の拡張や観光行動が影響しています。
夜間に車と衝突する「ロードキル」や、電柱にとまった際の感電事故が相次いでいます。
また、写真撮影や観察目的で近づきすぎることも、繁殖を妨げる原因になります。
保護の取り組み
北海道では、環境省・北海道庁・民間団体が協力して保護活動を続けています。
人工巣箱の設置、給餌池の管理、魚道の整備、電線への絶縁カバー設置など、実践的な支援策が進められています。
また、釧路市動物園では、けがをした個体の保護・治療・リハビリを行い、野生復帰を目指しています。
さらに2024年度には、環境省が「シマフクロウ共存ルール」を策定しました。
これは、観察・撮影・釣りなど人の行動が野生個体に与える影響を減らすための行動指針です。
具体的には、繁殖期(2月〜6月)は巣の周囲100メートル以内に立ち入らない、夜間のフラッシュ撮影を禁止する、釣りでは返しのない釣り針を使用する、などが定められています。
希望の兆し
こうした地道な努力により、一部地域ではつがい数の回復が報告されています。
羅臼や標津では、人工巣箱での繁殖成功例が続き、巣立ったヒナが成長して新しいつがいを作るケースも確認されています。
まだ安心できる状況ではありませんが、確実に前進していると言えます。
自然を守ることは時間のかかる作業ですが、その一歩一歩が未来につながっています。
保護活動と観察マナーの重要性
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージシマフクロウやエゾフクロウを守るためには、専門家の努力だけでなく、一般の人々の理解と協力が欠かせません。
観察や撮影を楽しむときに「ちょっとした思いやり」を持つことで、彼らの暮らしを大きく支えることができます。
専門家や団体の活動
保護団体や研究者は、次のような地道な活動を行っています。
・巣箱や給餌池の設置・点検
・繁殖状況や個体数の調査
・巣立ち雛への足環(あしわ)の装着による追跡調査
・河畔林の植樹や、川の自然再生プロジェクト
・感電防止用の電線改良工事
これらは冬の厳しい環境下でも継続されており、地域住民やボランティアが協力することも少なくありません。
研究結果は、環境省や大学の研究機関で分析され、全国的な保全政策に生かされています。
観察する側のマナー
一方で、一般の観察者にも守るべきマナーがあります。
特に繁殖期(2月〜6月)は、巣に近づくことを避け、長時間の観察やフラッシュ撮影を控えましょう。
フクロウは非常に敏感で、人の気配を感じると巣を放棄することもあります。
また、夜間の車のライトや大きな声もストレスの原因になります。
観察の際には、
・双眼鏡や望遠レンズを使う
・車は橋の近くで減速する
・釣り針は返しのないものを使用する
・ゴミは必ず持ち帰る
このような基本的なルールを守ることで、フクロウたちの環境を守ることができます。
「見守る」ことが最大の保護
自然観察は、ただ「見る」だけでなく、「感じて学ぶ」ことが大切です。
静かに遠くから見守ることで、鳥たちの自然な行動を知ることができます。
無理に近づかないことが、結果的に長く観察を続けられる秘訣でもあります。
観察者がマナーを守る姿勢こそが、次の世代へ自然を残す最良の方法といえるでしょう。
人との関わりが育む共存のかたち
 出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ
出典:もふもふ動物ほっかいどう イメージ北海道では、古くからフクロウは特別な存在として人々に敬われてきました。
アイヌ民族の文化において、シマフクロウは「コタンコロカムイ(村を守る神)」と呼ばれ、人々の暮らしを見守る神聖な鳥とされていました。
夜の森や川辺で聞こえる重厚な鳴き声は、村に安らぎと秩序をもたらすものと考えられ、フクロウは「森の守り神」として語り継がれてきたのです。
動物園と保護の連携
現代においても、この「守り神」はさまざまな形で人とつながっています。
釧路市動物園、旭山動物園、円山動物園などでは、シマフクロウの保護・繁殖プロジェクトが続けられています。
これらの動物園では、けがをした個体を保護・治療したのち、野生復帰を目指すリハビリも行われています。
また、人工繁殖によって生まれた雛の遺伝情報を管理し、血縁の近い個体同士が交配しないようにする「血統管理」も徹底されています。
こうした研究・教育・保全の三本柱が、国内外の保護ネットワークの中で連携して進められています。
(参考:釧路市動物園「シマフクロウ繁殖・保全事業」)
地域の人々による支え
行政や専門家だけでなく、地域住民の参加も欠かせません。
地元のボランティアが巣箱の設置や給餌池の維持を手伝い、学校教育でも「フクロウを守る授業」や観察会が行われています。
子どもたちが自分たちの地域に生きる動物を学ぶことで、「自然と共に生きる心」を育てています。
また、観光と保護を両立させる試みも広がっています。
釧路湿原や知床などでは、観光客が野生動物を安全に観察できるよう、ガイド付きツアーや観察距離のルールを設けています。
こうした小さな積み重ねが、地域全体の意識を変え、フクロウが安心して暮らせる森を取り戻す力になっています。
共生社会のこれから
人の暮らしと野生動物の生息地は、完全に切り離すことはできません。
私たちが使う道路や電線、河川の整備は、知らず知らずのうちに野生動物の命を左右しています。
だからこそ、私たち一人ひとりが「少しの配慮」を心がけることが大切です。
たとえば、夜間の車のスピードを落とす、森の伐採を減らす製品を選ぶ、観察時のマナーを守るといった行動が、確実に自然保護へとつながります。
北海道の森や川を守ることは、そこに生きるフクロウを守ることでもあります。
エゾフクロウやシマフクロウが再び森に響く声を届け続けられるよう、私たちも共に歩む姿勢が求められています。
エゾフクロウとシマフクロウの違いを知って自然を守る
最後に、この記事で紹介したポイントを整理します。
それぞれの特徴と保護の現状を理解し、北海道の自然と共に生きるための知識として役立ててください。
-
エゾフクロウは羽角がなく、白っぽいハート形の顔を持つ
-
シマフクロウは羽角があり、体が大きく力強い印象を与える
-
エゾフクロウの主食はネズミ類などの小動物である
-
シマフクロウは魚を中心に捕食する魚食性のフクロウである
-
エゾフクロウは北海道全域の森に生息する留鳥である
-
シマフクロウは北海道東部に限られて生息している
-
エゾフクロウの鳴き声は穏やかで「ホーホー」と聞こえる
-
シマフクロウの鳴き声は低く太い「ボッボッボー」と響く
-
体の大きさはエゾフクロウが約50センチ、シマフクロウが約70センチ
-
シマフクロウは絶滅危惧IA類として保護が進められている
-
魚道や給餌池、人工巣箱の整備などが保全の柱となっている
-
エゾフクロウも古木の減少によって巣の確保が課題になっている
-
フクロウ観察では距離をとり、フラッシュ撮影を避けることが大切
-
アイヌ文化ではシマフクロウが神聖な守り神として敬われてきた
-
自然と共に生きる意識を持つことが、未来のフクロウたちを守る鍵となる








